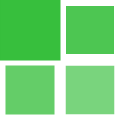アリ・美容・環世界そして言葉-ふと見た番組から考えたこと-
鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。
アリの観察から考える人間の世界
先日、『又吉直樹のヘウレーカ!』(NHK)で「好蟻性昆虫」についてアリ学者のお話を聞いた。アリは5000万年以上かわらぬ姿で今のような高度な社会システムを構築しているらしい。
しかし、そのシステムを逆用してアリに寄生する生物たちがいる。アリヅカコオロギ、ハネカクシ、ゴマシジミ、アリスアブなどだが、その寄生スタイルはきわめて秀逸である。そもそもアリはほとんど目が見えず匂いを頼りに生きている。
アリヅカコオロギは、見た目はアリと全く違うのだが、アリと同じ匂いをまとい、アリの習性である口吻をたたくと餌を与える反射を利用して、コオロギの前足で口吻をたたくことで餌を与えてもらう。
ゴマシジミ(蝶)は、その幼虫は甘い液をだして巣の中に運ばせ、アリの幼虫を捕食するが、女王アリと同じ音響を出して攻撃を避ける(すげー!)。
アリスアブはアリの巣に張り付くような平べったい形の幼虫で過ごす。動きはきわめて緩慢で壁と見分けがつかないが、ゆっくりと移動してアリの幼虫を捕食する(こわっ!)。蛹から成虫になったとたん、匂いが変わるので、アリの攻撃を避けるため一目散に巣の外へ逃れる。
面白いのは、アリたちは、このような寄生生物の存在が「見えてない(認識できない)」という点だ。ユクスキュルのいうアリの「環世界」には、このような寄生体は存在していないのだ。
ユクスキュルは、生物それぞれに独自の環世界(生きるための主観的な時空間)があると考えた。
アリにはアリの、カタツムリにはカタツムリの環世界が存在し、それが人間から見てどんなに奇妙なものであろうとも、進化で獲得した独自の環世界は、その生物を客観世界のなかで生存させるために必須のものである。
アリの寄生体は、アリの環世界には存在せず、ある意味で環世界の外部から侵入しているが、環世界のなかにいるアリには見えない。人間も同じように人間の環世界で生きているわけだが、アリと同じような「人間モドキ」が混じっていないのだろうか(『寄生獣』を思い出すなー)。
ひるがえって、人間をよく観察してみると、認知のかなりの部分を視覚に頼り、他の生物にはない「言語」を操り、外部の客観世界とは似て非なる「虚構世界」を共有して生きるという、きわめて珍妙な生き物だ。
視覚には錯覚や死角がある。言語は世界を解剖し再構成する道具だが、それ故の限界や死角がありはしないか。人間が脳内で構成する「虚構世界」は、それを人間同士が共有し利用しあってこそ意味がある。しかし、虚構を自在に使うが故の、見えない「呪い」のようなものがあるのではないか。

内側から出てくる不安をなくすための特効薬とは
少し話がずれるが、先日の『プロフェッショナル 仕事の流儀』(NHK)に、美容家の神崎恵氏が取り上げられていた。
彼女は美容のカリスマといわれ、さまざまな工夫をこらしたメイクでクライアントを美しくする「魔法にかける」という。
実際のメイク風景を撮影していたが、眉毛のかき方だけに2時間かける場合もあり、よく見ると相手の不安や思い込みをメイクすることでゆさぶっているようにも感じられた。
ある女性は、黒目が小さくて自信がなく10年間カラーコンタクトをつけないと人に会えないという。神崎氏は巧みな話術で安心させつつ、アイラインや目まわりの印象を変えることで、クライアントに自信を持たせた。
別の女性は、眉毛をなんどかいても納得いかない様子。それを見て時おりアドバイスしつつ、自分の力でやりきってもらう。その姿を見ながら、まるで心理カウンセラーのようだと感じた。
もちろん心理の専門家ではないが、相手の不安や弱い部分を認めつつ、メイクの力を借りて「変身」させることで、一種の「生まれ変わり」の体験をしてもらうような印象だ。
先ほどの“人間とはどのような生き物か”という議論で、人間は虚構に生きると書いたが、彼女を訪ねる女性たちは、自らの美意識、ときに歪んだ美意識、世間からの視線、生活の中での不安、そういうものを自らの顔に投影しているようにも思われる。
それらは、じつは人間の脳がつくりあげた虚構に過ぎないけれど、虚構ゆえに強く縛られ身動きがとれなくなっているのだ。そこを、メイクの力で一瞬間ゆさぶり、一歩前に出る勇気を与える。
美容とはそういう仕事のように感じられた。女性の場合には、「顔」というものが「その人」を表す大きな要素になっているがゆえに、強いこだわりが集中するのかもしれない。
それでは、男性の場合はどうか。
男性なら、仕事ができるか、経済的にはどうか、社会的地位はどうか、そういう評価が問われることが多い。そうなると、現在の立ち位置や評価に満足できない男性は、その評価に強くとらわれる可能性がある。
仕事ができない、お金もない、社会評価も低い、だから自信が持てない、女性の「顔」と同じように。そうなると、女性のメイクにあたる、自己像のゆさぶりというのは可能だろうか、そしてそれは何に該当するのだろうか。
たぶんそれは、違うコミュニティや人間関係を体験し、その人のありのまま、あるいは「生まれ変わったような」姿を、体験することかもしれない。家族や地域コミュニティに限らず、好きな趣味や同好の集まりなど、もっといえば「別の人間を演じること」、そういう「生まれ変わり」の体験が該当するのではないか。
こんなふうに書くと、さてはメンタリストか新興宗教かと警戒されるかもしれない。
でも、女性の「顔」も、男性の「自己像」も、虚構に過ぎないといっても、本人はどうしようもなくそれにとらわれているのである。やはり、「生まれ変わり」の実体験をすること以上の特効薬はないのではなかろうか。

病気の治療だけではなく、別の視点から見た医師の仕事
私たち人間は、言葉に縛られて生きる存在だ。言葉は便利な道具ゆえに、逆に人間を縛る。
これはデザインの領域ではアフォーダンスと呼ばれ、道具の使い方に人間が規定されていく姿を表している。
たとえば、コップを持つ、バットを握る、ハシゴをかけて登る、これらもすべてアフォーダンスの一種だ。当たり前のように見えるが、アフォーダンスには学習が必要である。ハシゴを見たことがない南方の原住民は、それが何だかわからなかった。しかし、いちど使い方を示すと、その後は当たり前のようにハシゴとして使い始めたとのこと。
もしかすると、人間の究極の道具である「言葉」も同じではないのか。
使い方がわかると当たり前のように使っているが、現実世界(リアル)を写し取る道具として、言葉という道具が完璧なわけではない。だから人間は言葉で表現できないものを絵画や音楽で認識しようとする。
そして、言葉の力が強力ゆえに、言葉の隘路に気づかない可能性があり、そこに「人間モドキ」が潜んでいる可能性もある。そして、自らの「自分はこういう人間だ」という呪縛を解くカギも、そのあたりにあるように思われる。
京極夏彦の小説『魍魎の匣』だったか、謎の殺人事件を追って迷路のような思考の末、じつは死体は最初から目の前にあったが見えていなかった、というオチだった気がする。
フレーミングといって、額縁に囲まれた風景は「作品」だが、いったん額縁を外すと背景に紛れて見えなくなる。額縁というフレームがあることで、人間はそこに別の意味を見出すようにできているのだ。
言葉もこの額縁と同じようなフレーム効果を持つかもしれない。
陰陽師の安倍晴明は言葉に「呪」をかけて式神として使うという。言葉は「コトダマ(言霊)」といわれるように、いったん発せられると独自の力を持ちうる。
宮本武蔵を描いた『バガボンド』で、若き武蔵は父の呪縛である「天下無双」という言葉に苦しめられる。より強い者を倒せば天下無双に近づくと考え、次々と敵を打ち倒す。そして柳生石舟斎を倒すため単身、柳生屋敷に入りついに石舟斎に対峙する。
しかし、そこで武蔵は不思議な体験をする。石舟斎は武蔵に「天下無双とは……ただの言葉じゃ」と静かに語りかける。言葉にとらわれることで強くなれる、しかし、そのとらわれゆえにもがき苦しむ。
言葉は世界を認識する道具であり、人間を高みへ導く力となり、そして同時に人間を拘束する檻ともなる。
そのように考えると、神崎氏のいうメイクで女性を「魔法にかける」という体験を、拡張して考えるなら、それまで無意識に自分を閉じ込めていた自己イメージや自己規定の呪縛を解くこと、「魔法から覚醒させる」というプロセスも、神崎氏の美容術の延長線上にあるものではないだろうか。
もしかすると、癒す人(Healer)としての医師の仕事というのは、言葉を使って、あるいは、言葉をあえて使わずにそこにいること(presence)で、病む人を「悪しき魔法から覚醒させる」というプロセスそのものを指しているのかもしれない。
そんなふうに考えるのは、うがちすぎた見方であろうか。アリの話からずいぶん離れてしまったけれど、ふと見た番組から、いろいろな妄想を広げていくのは、けっこう楽しいものだ。
Author: 谷口 晋一
こちらのページは、鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。