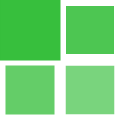私が大嫌いな、あの生き物について。
鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。
長かった夏がようやく終わり、日中は暑い日もあるけれど過ごしやすい気候になってきました(11月中旬に書いています)。皆様、いかがお過ごしでしょうか。私の勤務先がある山あいのこの町もやっと木々が色づき、秋だなあ、と窓から見て感じています。過ごしやすく、旬の食べ物も多く、私にとって一番好きな季節です。でも、1つだけ、どうしても許せない「秋らしいもの」があります。はい、そうです。カメムシです。もう書きたくもないので「ヤツ」とか「K」とかで呼びます。カメムシ愛好家の方はここで画面を閉じてください。回れ右。
本当に何なんでしょうか。窓をきっちり閉めていても入ってくる。いくら洗濯物の表裏を確認しても付いている。車のドアを開けるとドアのくぼみにいる。玄関出るといる。振り返らなくてもヤツがいる。余裕そうにノロノロ歩くのも、飛ぶのも正直許せません。においがつくとなかなか取れない上に、分泌物が体につくとめちゃくちゃ痛い。農作物を荒らす害虫であることも周知の事実。人間にとって害があるだけでこう言うのもどうかとは思いますが、やっぱりなぜ地球上に存在しているかが分からない。いなくても自然界は回っていく気がする。もちろん生き物ですから、食物連鎖の一角を担っていることは承知していますが。偶然とはいえ、とんでもない機能を進化で獲得しやがって。そう悪態をつきたくなるくらいには、とっても嫌いです。GとKはほんとに嫌い。

昨年度の大量発生は本当にしんどかったです。まさに地獄絵図でした。昨年下半期は育児休業の真っ只中。夫の仕事の都合で、海の近くの市街地のマンションに住んでいました。山からほど遠く、ニュースで大量発生なんて言っているけどここは安全地帯だろう、とたかを括っていたのですが、全然そんなことはありませんでした。玄関を開けたらいつも数匹はいるし、共用部にもいるし。網戸の内側にもいたときは窓枠に目張りしました。キンモクセイが近くにあるところだけ見ませんでした。キンモクセイすごい(虫が嫌う匂いなんだそうです)。こんな市街地でもこれだけ見るのだから、山あいの勤務地なんてもうどんなことになっているのだろう。想像するだけで震えました。しかも、暖冬で越冬したヤツが春、夏も普通に家の周りにいて、「これがこのまま秋冬にやってくるのか……」と絶望したものです。
そもそも、私がなぜヤツを嫌いになったかというと、明確なきっかけがあります。私が高校3年生の受験期も、ヤツが多かったのです。田舎生まれ田舎育ちなので、それまでそんなに気にしたことがなかったのですが、この年は大量発生したヤツらに悩まされました。部屋で勉強中、一瞬横の引き出しから物を取って体勢を戻したらノートの上にいたり。汽車の中で「何か臭いな?」と思っていたら、コートの袖口からヤツが出てきたり(しかもこれ、第二志望の受験に行く途中だったので、袖に臭いがついたまま受験するというガチのトラウマ)。極め付けは、学校で模試を受けていたら自分の横の窓枠にヤツがいて、ときどき飛んだりするもんだから怖くて全く集中できず、そのとき受けていた科目で自己最低点を叩き出した思い出。当時点数や判定に一喜一憂していた身からすると最悪の事態でした。大学受験という、それまでの人生で一番のストレスを抱えていた自分に追い討ちをかけてきたヤツの大量発生。あれから、もうずっとヤツは大嫌いです。そのシーズン、やっぱり大雪が降りました。

そう。ヤツが多い年は雪が多いって、昔から言いますよね。 昨シーズンも、こんなに多いんだから、予報では暖冬と言っているけどきっと大雪が降る、と身構えていました。結果、多少バッと降ったものの、全体的に見ると雪は少ない傾向でした。あれれ?テレビでも、カメムシを研究している先生が「カメムシと雪の量には相関がない」と解説していました。雪国では昔から人家にカメムシが侵入して越冬するので、冬とカメムシのイメージが結びついたのでは、という推測だそうです(頑張ってカメムシって書きましたが、やっぱり嫌なのでここからまた隠語に戻します)。
あれ、そうなの?でも、やっぱり昔からの言い伝えなら、多少は正しいのではないか、と思ってしまいますよね。先人の知恵って、ある意味長年のデータに基づいているわけですし。だけど、確かに昨シーズンは雪が少なかった。そして、福井テレビのニュースによると、実際に近年の積雪量とヤツの多さに相関関係はないそうです。温暖化の影響もあったりするのでしょうか。そして、今年。育休が明け、山あいの町に戻ってきて仕事を再開した私は、先述のとおり恐れていました。越冬した大量のヤツらが、さらに繁殖してやってくるのではないかと。スタッフの誰に聞いても「去年はほんとにすごかった」「ほぼ毎日家の中に出没」「洗濯物を外に干すなんて論外」「いすぎて感覚が麻痺した」。ある程度ヤツに慣れている方々が辟易するくらいって、どういうこと?ヤツ嫌いの私が、この病院でやっていけるの?と戦々恐々としていました。ですが。何だか少ないのです。ヤツ。山間部なので多少はいるのですが、恐れていたほどではない。もちろん、昨シーズンが多すぎて、相対的に少ない気がするのかもしれませんが、11月になってもあまり見ないのです。この辺りだけなのでしょうか。同僚とは「まだ日中暑いから、もっと寒くなったら出てくるのかな?」などと話しているのですが、患者さんから「今年は柿が不作」と聞き、それで少ないのかもしれない、と思ったり。
そんな2024-2025シーズン、積雪量は多くなる予想が出ています。ラニーニャ現象の影響だそうで、11月から急に寒くなり、全国的に平年並み〜多い積雪になるのだとか。やっぱり、ヤツの量と雪は関係ないのか。しかし、最近知り合いから、『ヤツが少ない方が雪が多い』説を唱える人がいる、という情報を得ました。その唱えている方のデータ(毎年家の周りで捕獲した数を記録しているそうです。すごいですよね)に基づく傾向なんだそうです。n=1ですが。うーん、ここまでくると何でもありですね。予報どおりここから急に寒くなれば、暖かいところを求めてヤツがまた顔を出してくるかもしれません。雪も多い、となれば、いろんな意味で厳しい冬になりそうです。実は私、当院に赴任した年に産休に入ったため、この雪深い町の冬を知りません。とりあえず、ヤツ対策も、大雪対策もしっかり備えておこうと思います。
みなさまも、この冬に山あいに寄られる際は、ガムテープやペットボトルと、スタッドレスタイヤやチェーンを、どうぞお忘れなく。
Author:竹安 つばさ
こちらのページは、鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。