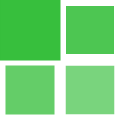懐かしい記憶と地域医療
鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。
9月中旬以降、朝夕すこし寒いと感じる。
目を転じれば、田んぼは黄金色で覆われ、そこかしこで稲刈りがはじまっている。庭の草刈りをしていると、この時期は妙に絡新婦の巣が目立つような気がする。彼らも最後のかき入れ時ということだろうか。
夜にはテレビやスマホを消して静かにしていると虫の音が耳に入ってくる。小さいころから何度も聞いたメロデイーだが、やはりいいものだ。心静かにその音に聞き入る時間はとても貴重だ。季節の移ろいを感じる風景というものがある。

季節の移ろいから考える、人々の潜在意識にある尊い記憶
今はコンバインで稲を一気に刈り取り、モミと稲わらに分離する。以前は刈り取った稲穂を竹で組んだハゼ木にかけて乾燥し、
モミは俵に入れ、稲ワラはそばに山のように積み上げる。見上げるほどのワラの山が出来上がると、そこは子供たちにとってごきげんな遊び場で、ワラ山から飛び降りたり、転げまわって大騒ぎしたものだ。ワラの中に入ると、ホコリっぽい日向の匂いがして、子ども心にそれが太陽のにおいだと思っていた。乾燥した稲ワラはまだ葉がギザギザしているので、夜お風呂に入ると手足のこすれた跡に湯がしみて痛かった。
今はもうない、こういう体験が、記憶の底から懐かしさと共に思い出される。人が生きていくときに必要とするのは、こんな記憶の断片ではないかと思ったりする。

共に病いに立ち向かうための『患者さんを診る視点』とは?
地域医療では人の病いや死に出会う。一人の人間が病むこと、死ぬことは、その人の人生に深く関わることだ。そして、その家族や友人にもつながっている。
だが私たち医師は、そのような存在に向き合っているということを簡単に忘れてしまう。つまり、糖尿病のAさん、喘息のBさんという、疾患という視点から相手を眺める癖がついているのだ。医学の進歩は専門細分化をすすめ、医療のシステムも大病院の専門診療科にかかる構造を作り出した。
医療環境がそのようになれば、患者は当然ながら糖尿病は糖尿病専門医に診てもらいたいと思うようになる。かくして、複数の病気をかかえる人は、複数の疾患別の診療科へ通わないといけなくなり、非常に時間のかかるものとなっている。もちろん、専門科はその疾患に注目して治療をおこなうので、きわめて機能的である。
しかし、いったい誰が「あなたという存在全体」を相手にしてくれるのだろうか。家庭医や総合診療医が、まさにその仕事を引き受けなくてはならないはずだ。私が病んだとき、病気のことしか聞いてくれない医師ではなく、子どもの頃のワラ山の「太陽のにおい」に共感してくれるような人に診てもらいたい。そういう願いを持っているのは、私だけではないはずだ。
その人の記憶を共にたどること、病いに立ちむかうその人ならでは源泉を見出すこと、そういうことも医師の仕事として大事な、<聴くという作業>に入るのではないだろうか。
Author: 谷口 晋一
こちらのページは、鳥取大学地域医療学講座発信のブログです。
執筆、講演、研修、取材の依頼はお気軽にこちらからお問い合わせください。